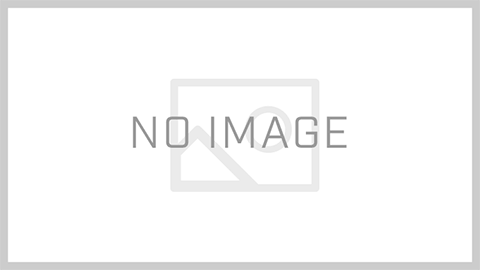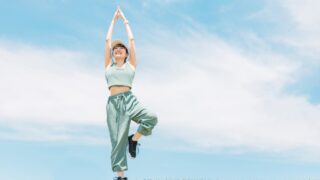こんにちは、fruitsloverです🍇
最近はどこでもシャインマスカットが売っていますね♡旬、最高♡
あのみずみずしい感じと、じゅわ〜っと口いっぱいに広がる甘さが、たまらなく好きです!
以前よりはお値打ちに売り出しているような気もしますが、それでもやっぱりちょっと高級品・・・。
スーパーに行っても、なかなか買えず、じーっと見つめて味を思い出して立ち去る⋯を繰り返しています笑
それにしても、あんなに美味しい果物を生み出してくれた生産者さんには感謝ですね😌✨
いつか頑張った日のごほうびに買おう⋯♡
さて、前回までは職場編として、4回シリーズでお話してきました。
職場での振る舞い方が自分のゆとりを少しずつ削っていき、周りに助けを求められないままパンクしてしまったところまでを整理してきました。
次は、私がうつになった要因3つ目。
親との関係についてを整理していきます。
「世の中にはそんな親子関係もあるんだな〜」と、気楽に読んでみてくださいね☘️

結婚前の私が育った家庭環境
みなさんは、自分が育ってきた環境をどう感じていますか?
仲の良い家族も、干渉し合わない家族も、家庭ごとに様々あると思います。
ここからは、私の家族を少し紹介させてください。
何でも親の了承を取るのが当たり前だった日々
振り返ってみると、小さな頃から何でも親に報告するのが当たり前、というのが我が家の風潮でした。
そういう関係性は、社会人になってからも、ごく当たり前のように続いていました。
___よくあることのように思われるかもしれませんが、いい大人が、自分で買う車の色や車種について親の意見どおりにしたり、母の不安解消のため夫婦の通帳を見せようと考えたりと、今の自分が振り返ってみても「行き過ぎている」と思えるほど、私の中には親の意見や顔色を伺うクセが染み付いていました。
「至って普通」だと思っていた私の家族
でも、「家族ってそういうものでしょ」と思っていましたから、何の疑問も持っていませんでした。
ケンカしたり、意見が合わないこともあったけど、漠然と「親の言うことは正しい」と思っていたように思います。
“結婚”が、家族を外側から見つめ直す機会になった
夫と結婚して、夫と過ごしていくうちに、自分の育った環境を外側から見る機会が増えていきました。
でもそれは、最初は受け止めがたい、苦しいことでした。

私の家族はこんな人たちでした
何が苦しかったかをお話する前に、少し、私の家族を紹介させてください。
・・・と言っても、登場するのは主に両親です。
私の価値観や思考パターンなどを形成していったキーパーソンだからです。
料理上手で過保護な母
母は、料理上手で食卓にはいつでも手作りの料理が幾品も並べられていました。
ちょっと過保護な面もあるように感じていましたが、それも愛の形なのだろうと思っていました。
パートをしながら、近所に畑を借りて野菜作りをしたり、庭に花を育てたり、縫い物も得意でした。
そんな母は、私には“家庭的な女性”として映っていました。
単身赴任が多いけど家族想いの父
父は真面目な性格で、バスや電車を乗り継いで通勤していたので、いつもきっちり時間を守る人でした。
仕事柄、単身赴任していた時期もありましたが、その時も夜にこまめに電話をくれていました。
私が進路で悩んでいた時期は、仕事で疲れていても夜遅くまで私の話を聞いて一緒に考えてくれました。
父のそんな姿は、私にとって社会人のお手本のようでした。
祖母との密接な関係
私の家は田舎にあり、父方の祖母が近所でひとり暮らしをしていました。
私が物心がつく頃には、祖母が毎晩我が家に来て、みんなで夕食を食べるというのが習慣となっていました。
母が夕食を作る間に、祖母が私の宿題を見てくれたり、一緒にお風呂に入ったり、折り鶴や編み物などを教えてくれていました。
祖母は早くに夫を亡くして生きてきたこともあってか、気の強い性格でしたが、私にとっては大切なおばあちゃんでした。
母と祖母との間にあった確執
母と祖母は、はっきり言って、折り合いの悪いふたりでした。
母が祖母の言葉に傷ついたり泣いている姿を、私は何度も見てきました。
母と祖母が、衝突して言い合いのケンカになることもありました。
母が料理を頑張っていたのも、姑である祖母からの評価を気にしてだったのかもしれません。
“家族とは一緒に過ごして然るべき”という価値観
それでも昔ながらの“家”という認識からか、祖母と一緒に過ごす生活は続いていました。
___今思えば、「相性が悪いから関わりを持たない」という選択を、父と母がなぜしなかったのか・・・
不思議ではありますが、当時の私は幼かったこともあり、「家族とはこういうもの」と思い込んでいました。
「私が取り持たなければ」子どもの頃からの仲裁役
父は、妻に母親との付き合いをしてもらっているからか、揉め事となってもその場を治めるのみで、お世辞にも上手なバランサーにはなっていなかったと思います。
しかも父は、単身赴任で不在の時もありました。
そうした状況の中で、私が仲裁役をしたり母を慰めるのは、必然的だったと思います。
母に八つ当たりされても寄り添って、時には空気を変えようと顔色を伺って行動したりもしていました。
___こうした背景もあり、私は“子どもらしい子ども”というより「しっかりしたいい子」と見られることが多い子ども時代を過ごしていました。

成績と学歴へのプレッシャー
勉強面でも、両親からの偏った価値観の中で「親の求めるもの」に対して成果を出そうと努力する子ども時代でした。
努力と100点が当たり前だった環境
母から言われてすごく印象的だったのが「小学校中学校のテストは、出来て当たり前」という言葉です。
確か、良い点をとったテストを見せた時に言われた言葉でした。
両親から褒められた記憶はほとんどありません。
だから、どれだけ勉強を頑張ったかや、平均点と比べてどうだったかよりも、出来なかったところに目が行きやすくなっていきました。
___出来て当たり前のことだから、というベースの中で勉強していたため、幸か不幸か、小学校中学校での成績は良い方だったと思います。
ただ、そういう価値観でいたため、良い点数でも嬉しいとか誇らしいと感じたことはなく、ミスしたところを怒られないかとか、他の子達はなぜ70点で喜べるのかとか、ちょっと周りの子達とはズレた感覚だったと思います。
「私立大や浪人は無理」というプレッシャー
高校生になって、“出来て当たり前”の枠から卒業したことで、成績は一気に落ちました。笑
でも、受験の年にそのツケはちゃんと自分に帰ってきました。
「お金ないから私立大や浪人はやめてね」と、冗談なのか本気なのか、よくその言葉をかけられていました。
私は真に受けて、国公立大学を目指すことにしました。
母の言葉は、私にとって重く、逃れられないプレッシャーでした。
それでも母は、自分の言葉がどれほどの重みなのか、気づいていなかったのかもしれません。
親が納得できる学歴を残すことが目標になった
今思えば、母の教育方針は偏りが多かったと思います。
点数や順位、通知表など、分かりやすい成績に焦点が当たりやすかったです。
祖母の手前、父方の従兄弟と比べたり優位に立ちたい気持ちもあったのかもしれません。
父も、自身も学歴にそこそこの自信があったからか、学歴や成績を重視する価値観でした。
両親の納得いくような成績を出さなくちゃという私の思考は、こうして出来上がっていきました。

夫からの指摘で初めて知った「毒親」という言葉
大人になり、夫と出会い、結婚しました。
夫という別の価値観の人と生活する中で、初めて知ることや気づくこともたくさんありました。
その中のひとつが「毒親」という言葉です。
毒親という言葉のインパクト
毒親(どくおや: toxic parents)とは・・・
毒と比喩されるような悪影響を子供に及ぼす親に対して、1989年にスーザン・フォワード (Susan Forward) が作った言葉である。
『毒親』Wikipediaより引用(更新日時:2025年8月16日、閲覧日時:2025年10月21日)。
学術用語ではなく、スーザン・フォワードは「子どもの人生を支配し、子どもに害悪を及ぼす親」を指す言葉として用いた。
初めて“毒親”を知ったときは、その言葉のあまりの強烈さに、自分が毒親育ちなのだと受け入れることが出来ませんでした。
結婚後のケンカで指摘された「境界の薄い関係性」
もともと別々に生きてきたふたりが、結婚して生活を共にする。
その中では、すれ違いや意見の違いを感じることもあると思います。
私たち夫婦も、そうしたケンカや噛み合わなさを何度も体験していました。
そんななかで夫から、私と両親との境界の薄さを指摘されました。
「過干渉」「支配的」「過度な期待」…頷ける特徴
最初はムッとしましたが、言われてみれば確かに・・・
親には包み隠さず何でも報告するのが当たり前だと思っていたし、両親が私のプライベートなこと(例えば、夫婦の旅行の頻度から家を建てる場所の候補まで⋯!)にも意見することや私がそれを受け入れることが普通だったり・・・。
過干渉や過度な期待のなかで生きてきた感覚もあったので、葛藤しながらも反論できないと感じました。
「衣食住に不自由なく育ててもらったのに」否定し続けた私
でも、経済的困窮や暴力暴言というような、明らかに劣悪な家庭環境だったわけではないため、実の両親に“毒親”という言葉を当てはめることには、罪悪感も違和感もありました。
両親を否定することは親不孝で罰当たりなことのように思えました。
また、自分自身の人生も否定してしまうんじゃないかという怖さもありました。
“毒親育ち”だと受け止められない気持ち
私と両親だけでなく、夫との生活にも入り込んでいたその“境界の薄さ”を、認められるようになるまでには、とても長い時間がかかりました。
自分の育った家庭を客観的に見つめることも、「ちょっと変かも?」という疑問を認めることも、苦しくて目を背けたくなることでした。
何度も夫とケンカしたり話し合ったりしていましたが、ちゃんと“毒親育ち”だと向き合って認めることが出来たのは、うつ病になってカウンセリングを受けるようになってからです。
10年近くかかってやっと、認めることが出来るようになったのです。
毒親育ちを認めることで、やっと今の自分の家族を大切にする視点が持てました。

今日はここまで・・・
今日もここまで読んでくださって、ありがとうございます。
親との関係は、私のうつ病にもたくさん影響がありました。
でもそれは、簡単には言葉にできない色んな気持ちや背景などが折り重なって生まれたものだと思います。
【親との関係編】はまたボリュームのある記事になると思いますが、どうぞお付き合いください🙇
では、次回の記事でまたお会いできますように🍀